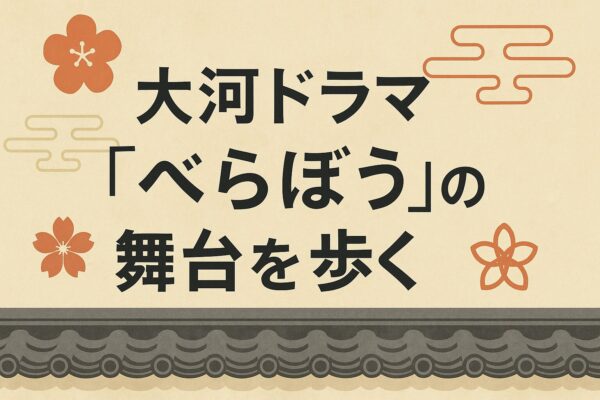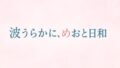2025年度大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢話~』めっちゃ面白いです!!毎回時間が通り過ぎるのがあっという間。ということで、ドラマに登場したゆかりの場所をいくつか巡り歩いてきました。
以下、ドラマの登場人物ゆかりの地を巡って江戸散歩した各地についてご紹介します。蔦重ゆかりの地歩きの参考になればこれ幸いにござります。
大河ドラマ『べらぼう』ゆかりの地を歩く ー蔦屋重三郎が育った吉原エリア①ー
蔦屋重三郎生誕の地
大河ドラマ『べらぼう』の序盤の舞台、それが江戸の「吉原」です。ドラマの中では、若き蔦屋重三郎がこの吉原で育ち、さまざまな出会いと別れを重ねながら、後の「出版界の風雲児」へと成長していきました。
吉原は江戸幕府お墨付きの遊郭!
江戸時代、遊郭(ゆうかく)と呼ばれる場所は数あれど、幕府が公に認めたのは吉原だけ。
もともとは現在の人形町あたりにありましたが、明暦3年(1657年)の大火をきっかけに、現在の台東区千束3~4丁目付近に移転。これがいわゆる「新吉原」です。
移転後の吉原は、遊郭だけじゃなく、商店や茶屋も軒を連ねて江戸文化の発信地として大いに栄えました。

ここで、俺についてちょっと語ってみるぜ
大河ドラマの主人公である蔦屋重三郎(本名は「柯理(からまる)」)は、1750年に吉原で誕生、7歳のときに両親が離婚した後「蔦屋」の屋号で吉原の引手茶屋を経営していた喜多川氏の養子に迎えられます。
ドラマでは…設定がちょっと違う?
「べらぼう」では蔦重の育ての親は駿河屋市右衛門(演じているのは高橋克実さん)ということになっていますが、これはドラマオリジナル設定だそうです。喜多川氏については未だに謎が多いため、当時の「吉原細見」に名前が載っていた有名茶屋「駿河屋」の名前を拝借したのでは、とも言われています。
ちなみに重三郎の義理の兄とされる次郎兵衛(中村蒼くんが演じてます)は、駿河屋の息子ではなく喜多川氏の実子という説が有力です。

ドラマの中で親父様と義兄さんは俺にとって”飴と鞭”みたいな存在
吉原の入口「吉原大門交差点」と「見返り柳」
吉原への入口となるのが現在の東京都台東区千束の「吉原大門」交差点。この場所に大門があったと誤解される方もいると思うのですが、実際の大門跡はさらにその奥にあります。
今は車がバンバン行き交う大通りですが、かつてここは「日本堤」と呼ばれた土手で吉原へ通じる道だったと言われています。江戸の町の中心から隅田川を舟で北上して吉原を目指し約1キロの道のりを歩いたとか。

関東大震災後に町の整備で日本堤は壊されたけど「土手通り」という名称は今でも残ってるよ。
この交差点脇(ガソリンスタンド前)に一本の柳の木が立っています。

吉原遊郭で遊んだ男たちが、帰り道にふと立ち止まりこの柳を振り返って眺めたという伝説があります。ことから「見返り柳」と呼ばれるようになりました。
大きな災害や戦火で失われるたびに植え替えられてきたそうで、現在のものは6代目に当たるそうです。
五十間道(衣紋坂)

見返り柳の角を曲がった道は「衣紋坂」と呼ばれていました。なぜその名前が付いたかというと、遊郭を目指してやってきた男性たちがこのあたりで身なりを整え(着物の襟を整えてた)ながら歩いていたからなんだとか。自分を良く見せようと一所懸命(必死!?)だったんでしょうね。

鼻の下伸ばして羽織の紐を直してる男たちを想像するとちょっと面白いだろ?
写真をよく見てもらえるとわかるのですが、奥の方が右に大きくカーブしてます。一説によれば、日本堤(船着場から吉原へ続く土手道)は大名行列も通った為、お殿様に”歓楽地の入口=吉原大門”を見せないようにあえて鋭角なS字カーブにしたそうな。

お殿様の行列が通るときに吉原の門が見えたら“体裁が悪い”っていうのが当時の江戸幕府の考えだったらしい。まぁ、そりゃそうか。
衣紋坂を抜けた先から、吉原大門へとつながる道は五十間道(ごじっけんみち)と呼ばれています。

「衣紋坂から大門の入り口まで約五十間(ごじっけん)=およそ100メートルほどの距離だった」ことが由来。

吉原で開店した本屋・耕書堂はちょうどこのあたり
現在その想定場所には「浮世絵カフェ蔦重」という小さな喫茶店があります。

私が訪れた日はちょうど休業日で中に入れず(汗)。土日休日は基本的にお休みのようでした。詳しい営業日は公式のインスタを参考にしてください。
このお店の外壁には「見返り柳から吉原大門まで」の地図が貼ってあり、蔦重の足跡をたどるのにぴったりです。聖地巡礼に訪れた際は要チェック!

この略図によれば、蔦重の義兄・次郎兵衛が経営していた「引手茶屋」もこのすぐ近くだと想定できます。蔦重は最初この引手茶屋の業務をこなしながら貸本屋を営んでいました。

ドラマでは遊び人で仕事に無頓着な義兄さんより俺の方が店を回してたように描かれてたけどな(笑)
蔦重が茶屋から独立し新しい本屋を開店させるくだりのエピソードは、大河ドラマ第14回『蔦重瀬川夫婦道中』で描かれていました(大黒屋から「お前も一国一城の主にならないと!」と背中を押された蔦重が五十間道で空いた店舗を買い取り本格的に耕書堂を開店させるくだり)。
【大河ドラマ べらぼう】第14回「蔦重瀬川夫婦道中」のあらすじ 4月6日放送
検校と瀬川、囚われの身に。果たして蔦重とは……。相関図や「徹底ガイド」も読めます👇横浜流星さん主演 #大河べらぼう #横浜流星 https://t.co/ZaVO42iQE4 pic.twitter.com/FRxMi0Ug3L— 美術展ナビ (@art_ex_japan) March 30, 2025
ただこの回は瀬川の分岐点になるエピソードがめっちゃ切なかったんですけどね。
吉原大門跡

吉原遊郭への唯一の出入り口だった吉原大門。現在は簡素な街灯付の柱のみがその名を残しています。大門によって遊郭と外の世界がはっきり分かれていました。

かつてこの場所にはとびきり立派な“冠木門(かぶきもん)が立ってたんだ!
門をくぐったすぐのところには面番所と四郎兵衛会所いう監視所があり、奉行所から派遣された岡っ引きや番人が常駐していたと言います(今でいう交番のような役割)。特に女性の出入りは厳しく監視されていて、遊女が許可なく門の外に出ていくこと(足抜け)はほぼ不可能だったとか。
大門跡の足元には、吉原と耕書堂の関係を紹介する案内板が設置されています。

ちょうどこのあたりに面番所が設置されてた感じでしょうか。
『べらぼう』でもたびたび登場していた吉原大門のシーンですが、一番印象深かったのは第10回「『青楼美人』の見る夢は」だったかと。
瀬川の花嫁道中…
「これから私は検校の妻として生きて行かなきゃならない、生きていくんだ、と蔦重(#横浜流星)への思いに蓋をして、前だけを見て大門をくぐりました。本当に複雑で、苦しい花嫁道中でした」
— ステラnet (@steranet_nhksc) March 9, 2025
鳥山検校に身請けされた瀬川は、”吉原”の未来のため蔦重への想いを封印し凛とした花嫁衣装で吉原大門をくぐりました。哀しく儚く美しい瀬川の花魁道中や、蔦重と瀬川がお互いまっすぐ前を向いたまますれ違うシーンなど見応えたっぷりな神回だった(放送当時ボロ泣きしたなぁ)。このシーンでの吉原大門は未だかつてないほど圧倒的な存在に見えたのが忘れられません。

愛する瀬川と結ばれることはなかったことは辛かったけど、新しい耕書堂始動に向けて俺は前を向いたんだ!
門をくぐったその先にまっすぐ延びる道は吉原遊郭のメインストリート仲之町(なかのちょう)通り。まさに吉原の「顔」、夢と欲望と粋が交差する舞台でした。およそ250メートルあります。

道の両脇には多くの引手茶屋が軒を連ねていたと言われています。ちなみに蔦重たち営んでいた茶屋があったのは前にも書いた通り門の外の五十間道沿い。
茶屋とはすなわち吉原の案内所。お客さんの希望に沿ったお店を紹介する仲介業者のような役割を担っていました。最高ランクの店は茶屋を通さないと登楼できない仕組みになっていたりと、吉原の中でもかなり重要な存在だったことが伺えます。
仲之町では様々な季節限定のイベントが行われたそうですが、有名なのが春の桜。毎年3月下旬ころになると植木職人により数千本の桜の木が植えられたと言います(実際は数百本かも?)。桜1本およそ150両(現在の価値だと800~900万くらい)で散ったら撤去されていたらしい。これを毎年繰り返してた吉原…いかに大金が落ちてきていたかが分かるエピソードです。

仲之町通りで一番最初に思い浮かぶのはやっぱり花魁道中だけどな
ちなみに、遊女のいる妓楼は仲之町通りから左右に延びる細い道沿いにありました(表通り)。現在もその場所には風俗店が多く立ち並んでいるので、明るい時間帯でも一種独特の雰囲気が漂っています。この場所の歴史散策はあまりお勧めできないかも(特に女性の方)。
見返り柳~大門跡までのアクセス地図
最寄り駅とアクセス
① 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」【最も便利】
出口:3番出口 / 徒歩:約12〜15分
② 東京メトロ日比谷線「入谷駅」
出口:1番出口 / 徒歩:約15分
③ つくばエクスプレス「浅草駅」
出口:A2出口 / 徒歩:約15分
④JR山手線「鴬谷駅」下車
都バス「南千住汐入」行き「吉原大門」か「浅草5丁目」 / 徒歩:約15分
吉原エリア散策レポの続きは次の記事にて。
大河ドラマ『べらぼう』感想一覧